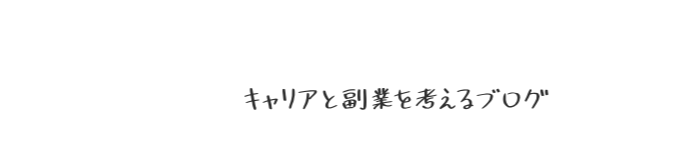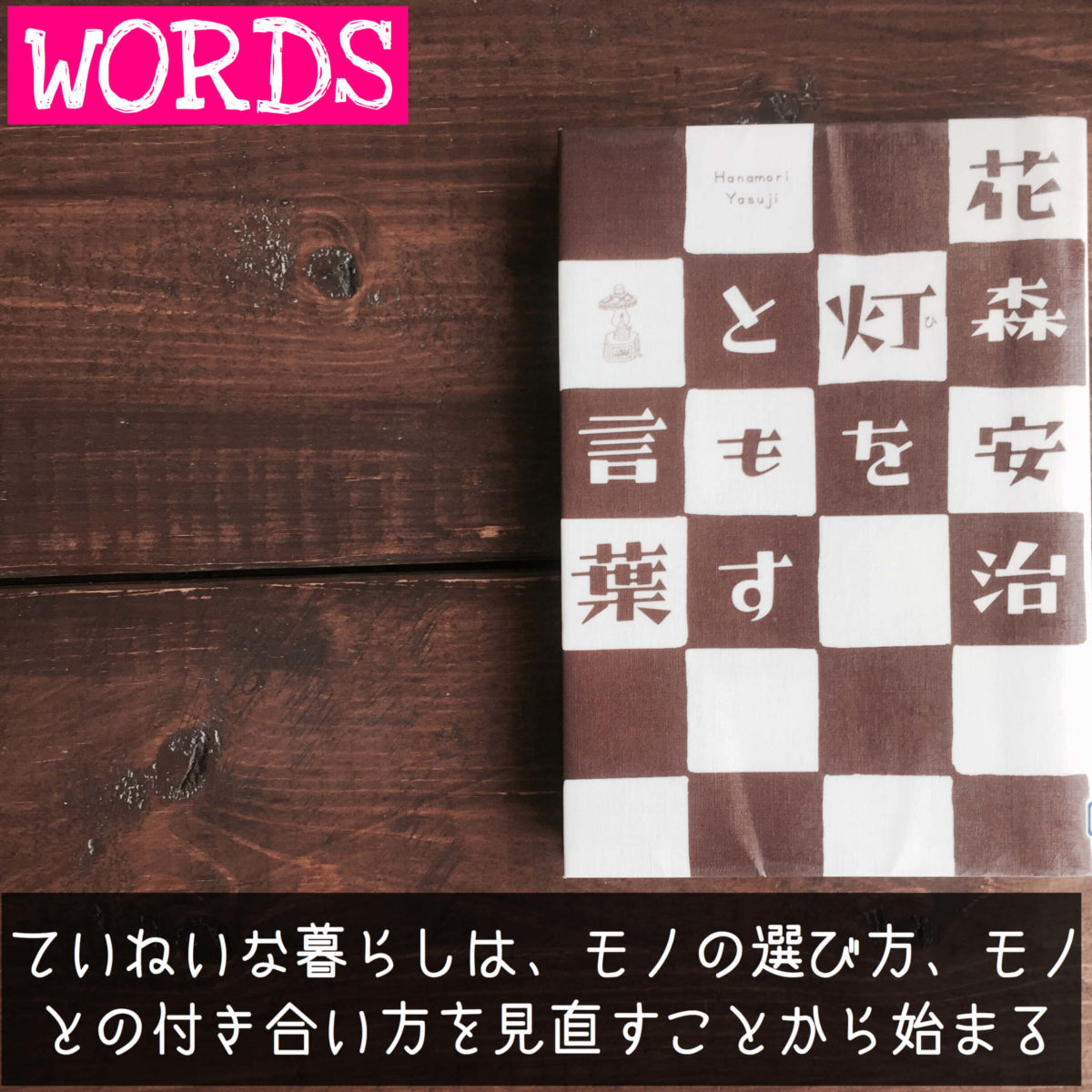今日の一冊は花森安治さんの「火を灯す言葉」です。
花森さんが初代編集長を勤めた雑誌 「暮らしの手帖」が創刊されたのは、戦後間もない1948年でした。
戦時中、捨てることを余儀なくされた「当たり前の暮らし」。けれど、それこそが人間にとって最も重要で最も守らなくてはいけないものだと、花森さんは気付いたようです。
戦争が終わり、当たり前だけどかけがえのない暮らしを見つめ、より良い暮らし方を提案されてきました。
本書は、「美」「世の中」「戦争」「おしゃれ」といった、私たちの生活に密接に関わることがらについての考え方を、花森さんの視点で教えてくれる一冊です。
静かな口調の奥に潜む、生きていくこと、暮らしていくことへの激しい想いは、ただなんとなく毎日を過ごしている私たちに火を灯す言葉になるかもしれません。
【花森安治の名言が疲れた心に火を灯す】
花森さんは本書の中で、暮らしの中でのモノとの関わり方の大切さを強調されています。
ユニクロを代表するようなファストファッションや、プチプラと呼ばれる安価なモノを生活の中に組み込むことは、今のこの国全体の流れになっています。
「これがいい」ではなく、「これでいいか」の考え方は、日常の中のモノだけでなくあらゆる場面で見られるようになりました。
夢を持たず、公務員のような安定した仕事でいいと考えたり、海外に憧れるけれど手軽な近場の旅行でいいと考える人は非常に多く見受けられます。
誤解してほしくないのは、ファストファッションを否定しているわけでもプチプラ商品を卑下しているわけでもなくて、モノを大切にする心を持てているかと言うことです。
それは自分の人生としっかり向き合っているかということにもつながります。
何千円とするお茶碗を買っても、結局大切に出来なければ何も豊かになりません。
安森さんは本書の中でモノを大切にしていない状態を次のように言っています。
「みがいてもやらない。ふきこんでもやらない。つくろってもやらない。こわれたらすぐ捨ててしまう。古くなったらすぐ捨ててしまう。見飽きたら新しいのに買いかえる。」
モノを大切にするということはどうすることなんでしょう?
あなたにはあなたなりの「大切の仕方」があると思います。
言葉にすることで大切だということを伝えることも出来ます。お金をかけて尽くすことで大切だということを伝えることもできます。
僕なりに大切の仕方はなんだろうと考えてみると、それは「手を当てる」ということではないかと思いました。
手を当てて、そのモノを見つめ、想ってみる。その行為が、自然とモノを大切にする気持ちを育むように感じます。
そしてその時間を持つことは、丁寧に日々を暮らしていくのに必要な時間となるのではないでしょうか?
昔の人は、苦しんでいる人がいるときには手を当ててあげて治癒していたと言います。それがそのまま「手当て」という言葉として今も使われています。
薬や医療技術が発達していなかった頃、人に出来ることは、手を当ててあげることくらいだったのかもしれません。
しかし、手を当てて相手の回復を願う思いは、相手を治癒する何らかの力を持ったのかもしれません。それはモノに対しても同じなのではないかと思います。
暮らしを豊かにする「モノを大切にする気持ち」。この本を通して、新しい暮らし方が見つかるかもしれません。
【胸に残った言葉たち】
「ぼくらの暮らしを守ってくれるものは、だれもいないのです。ぼくらの暮らしはけっきょくぼくらがまもるより外にないのです。」
「物を大切にするということは、やさしいこころがないとできないことだった。」
【火を灯す言葉 商品情報】
【LIFE WORK CAFEのおすすめ記事】
【厳選】キャリア相談が出来るおすすめカウンセリング5選|仕事や転職の悩みが解決する有料サービスを比較
【最新5選】動画編集を副業に出来るスクールはどこ? オンラインでスキルと稼ぎ方を学んで収入アップ
【社会人必見】Webデザインを副業に出来るおすすめスクール5選|Web制作を働きながら学んで最短で稼げる
【7選】稼ぎたいWebライターにおすすめの講座と初心者向けWebライティングスクール|オンラインで副業ノウハウが学べる
【転職向け】Webマーケティングスクールおすすめ5選|未経験からWebマーケターへ就職する最短ルート