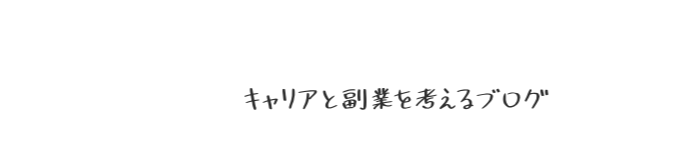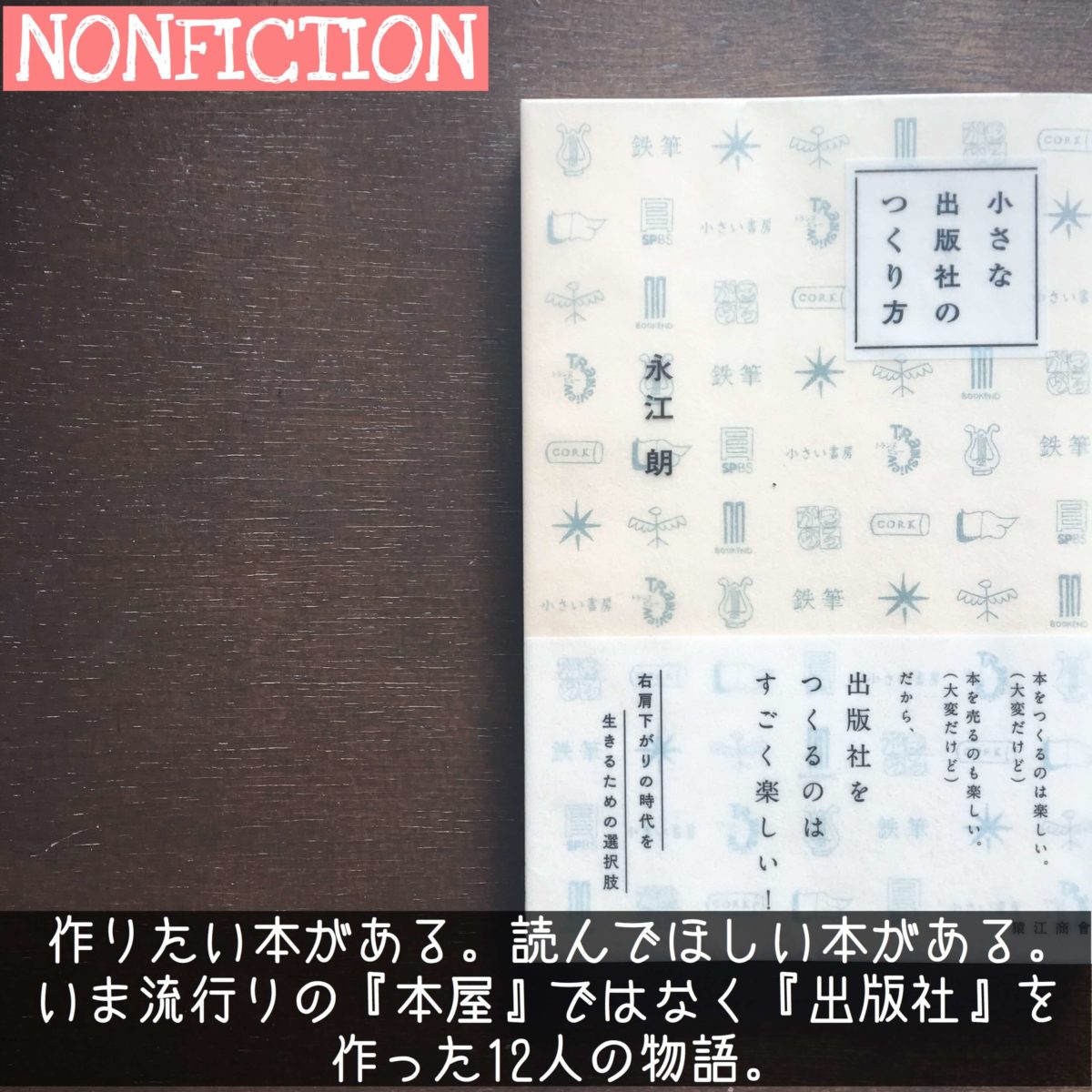本日は永江朗さんの著者「小さな出版社のつくり方」より、これからちいさな出版社をやりたい人が覚えておきたい6つのことを抽出してお伝えしたいと思います。
こちらの本では、12人の小さな出版社を始めた方たちと著者とのやり取りがまとめられています。ひとりで始めた方や同志で会社を立ち上げた方、さらには私たちのイメージする出版社ではなく「営業代行」を行う出版社や、「作家と作品のエージェント」を生業とする会社を始めた方など様々なタイプの「小さな出版社」が登場します。
出版業界は「再販制」や「委託販売制」といった特徴を持っており、小売りの中でも特殊な業界だということを聞いたことがある方もいるかと思います。また、書店の数や出版点数の減少により、斜陽産業を代表する業界ともなっています。
そんな中でも既存の体制に疑問を持ち、そこから新たなムーブメントを起こそうという動きは始まっています。この本に登場するのは、その新たなムーブメントを牽引する12名とも言えます。
最近は独立系書店と言われる、「小さな本屋」に関する本が多く出版されていますが、本書のように「小さな出版社」を作りたい方向けの本はあまり多くは出ていないので、出版社側に興味がある方には参考になる一冊だと思います。
【本屋さんを作りたい人にはこちらがおすすめ⬇︎】
【本屋をやりたい人必読!本屋TITLEは本屋になりたい人の教科書的存在】>>
【小さな出版社をやりたいときに覚えておいてほしいこと】
「旗印を持つ」
まず大切なことは、「うちの出版社はこんな出版社です」と確かに言い切れる強み(旗印)を持つことです。
少人数でちいさな出版社をやっていくとなると、大手出版社のように、年間で数十点数百点という刊行物を出すことはほとんど不可能です。年間2.3冊しか世に送り出せないのに、雑誌も文芸書も絵本もビジネス書も・・・というのでは、出版社としての色が見えてきません。
強みをはっきりさせるというのは、小商いを志す全ての人に言えるでしょう。小さなスペース、少ない人数、少ない点数だからこそ、逆にこれなら負けないという「強み」を押すことが重要です。
「大手問屋を通さない」
出版業界では、出版社と書店の間に日販やトーハンといった取次店というものが存在します。出版社は本が出来上がったら取次店に入れ、取次店がどの書店に何冊送るか(配本するか)を決め、書店に送られます。
本屋を始めるにあたってもこの取次との契約はネックで、実績や信用、さらには小さいお店でも数百万単位の保証金が必要になっています。出版社側も同様で、小さな出版社には厳しい信用条件が課されます。
では、取次店との契約なしでは出版社は始めることが出来ないのか。本書に登場する11の小さな出版社は、その多くが取次店との契約をせずに、直販という形で書店と取引をしています。
直販というスタイルは書店側の手間も増えることもあり、煙たがられることも多かったようです。しかし、書店側も生き残りのためにより利益率の高い商材を入れたり、異業種と提携したりする中で、直販での取引も以前より緩和されてきているようです。
今後小さな出版社を始めるのであれば、直販やJRCや営業代行といった「大手取次を介さない」流通方法を取るべきかもしれません。
「文庫で出版する」
文庫に対して使われる言葉は「単行本」と呼ばれるものです。大体1400円ぐらいの値段で販売されていますので、文庫よりも値段が高く、その分売れれば利益の額も大きいとは言えます。
しかし単行本の場合、書店に陳列される期間は、ほんの1週間から数か月だと言われています。文庫は出版社別のところや著者名順に並べられているところがありますが、多くの書店では新刊棚も充実しており、単行本よりも長期間で店頭に並ぶ可能性があります。
さらに書店に足を運ぶと実感するかもしれませんが、書店にいるお客さんの多くは、雑誌か文庫かコミックの棚にいます。つまり単行本は書店に並ぶ期間が短くて、しかも気付いてすらもらえないかもしれないということです。
本の出版といえば「単行本」の方をイメージされる方も多いと思いますが、本書に登場する小さな出版社では、初めから「文庫」としてしか出版しないという出版界の常識を破る選択をした出版社もあるのです。
「著名な作家にお願いする」
小さな出版社を始めるにあたり、実績や信頼がない分どのような本を出すかで、書店に並べてもらえるかどうかが変わります。本書の中でも、一冊目の本は著名な作家さんでなければと考え、出版依頼をされた方もいます。
もともと出版社に勤めていて、お願いできる作家さんがいればいいかもしれません。ですが、コネがない場合は自分からアポイントを取ってお会いして熱意を伝えるなど、動きまくらなくてはいけません。
本書に登場する出版社「小さな書房」の安永さんは、お願いしたい作家さんの講演会に赴き、手紙を渡して出版社を立ち上げる旨と執筆の依頼をしたと言います。
また、本書ではありませんが幻冬舎の見城徹さんは自著「荒野の読書」で、執筆の依頼をするに当たり、その作家の一番好きな本をすべて暗唱できるように読み込んでからお願いの場に臨んだと言います。
小さな出版社が著名な作家さんに書いてもらえる可能性は決して高くありません。それでも信用も実績もない出版社にとって、著名作家の本を出版するということの持つ意味は大きいと思います。
その奇跡は、たったひとりの熱意と行動力から生まれるのかもしれません。
「印刷会社で教えてもらう」
本書に登場する方々は、多くがもともと出版社勤めである程度出版の流れについて熟知している方がほとんどでした。ですが、「本を出したい」という熱意はあるものの全く知識もコネもない場合、どうやったら本を作ることが出来るのでしょう。
「小さな書房」の安永さんは、初めての本を作るにあたって、とにかく印刷所を回っていろいろなことを教えてもらったそうです。本の内容にあたるデータの入稿方法や紙の選び方、サイズや値段など。いくつかの印刷所に作りたい本の様式を伝え、見積もりを取ってその中から選ぶのがいいでしょう。
また、全くの初心者であるなら、本のつくり方を教えてくれる本として、サンクチュアリ出版の「自由であり続けるために、僕らは夢でメシを食う 自分の本」も読んでみるといいかもしれません。
「自社サイトでの直接販売とSNS・地方新聞を使った宣伝」
本が完成しても売れなければ2作目3作目と作ることは出来ません。大手出版社であれば、作って取次店に卸せばあとは自動で全国の書店に配本してくれますが、小さい出版社であればそうはいきません。
置いてくれそうな書店に電話をしたり、FAXをしたり、直接出向いたりして、なんとか本を書店に並べてもらうことは重要です。
しかし、それ以外にもやるべきことはあります。まずは自社サイトを立ち上げ、そこで直接書店ではなくお客様が購入できるようにすることです。そうすれば、書店に7掛け8掛けで卸すよりも利益率は高くなります。
自分で作って自分で売る。この本来の売買の仕組みを忘れてはいけません。
また、そのためにも書店以外での認知の場を増やす必要があります。その方法としてSNSを使った宣伝が今は最も有効だと言われています。インスタグラムやツイッター以外にも、読書系のWEBサービスは多数存在しています。そうしたものをいくつも使いながら少しでも多くの人に本の存在を知ってもらうことが重要だと思います。
また、新しく小さな出版社を始めるということはなかなか珍しい出来事になります。そんな「珍しい出来事」を探しているのがメディアです。特に新聞は本との相性も良いので、ぜひ出版社の立ち上げ時や本の出版時にはお知らせしましょう。記事にしてもらえるかもしれません。
詳しいやり方は「プレスリリース」という言葉で調べてみましょう。
【好きなことで生きていく】
小さな出版社の多くは、作業の猥雑さや流通の難しさと闘いながらも、丁寧に一冊一冊を作っています。大量生産大量消費時代はとうに終わり、価値観が多様化するなかで、気持ちを込めて大切にモノを作っていくというのはこれからの時代のメインストリームになっていくのではないかと思います。
本書では残念ながら、具体的な本のつくり方や出版社の続け方に関しての話は少なく、また「出版社をする楽しさ」のようなところの聞き出しも薄かったような印象を受けました。
ですが、本を世に送り出すために出版社を作った方たちのリアルがそこにあるのかもしれません。これから出版社を作りたいと思った方にとってスタートとなる一冊だと思います。ぜひ読んでみてください。
<商品情報>
【LIFE WORK CAFEのおすすめ記事】
【厳選】キャリア相談が出来るおすすめカウンセリング5選|仕事や転職の悩みが解決する有料サービスを比較
【最新5選】動画編集を副業に出来るスクールはどこ? オンラインでスキルと稼ぎ方を学んで収入アップ
【社会人必見】Webデザインを副業に出来るおすすめスクール5選|Web制作を働きながら学んで最短で稼げる
【7選】稼ぎたいWebライターにおすすめの講座と初心者向けWebライティングスクール|オンラインで副業ノウハウが学べる
【転職向け】Webマーケティングスクールおすすめ5選|未経験からWebマーケターへ就職する最短ルート