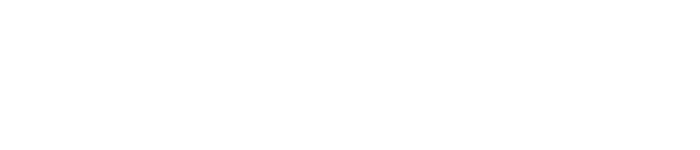本屋に憧れて、自分の好きな本を集めたブックカフェを始めて9年目になります。
この記事では本屋を開業したい方に向けて、以下のテーマでお伝えしていきます。
ひと昔前まで、本屋を始めるには数千万円の費用がかかると言われていました。
さらに本の利益率は他業種に比べて圧倒的に低く、さらにインターネットの興盛によって出版業界は斜陽産業。本屋を開業して経営していくことは非常にハードルが高いことだったのです。
しかし、2010年代は独立系書店や本のセレクトショップと呼ばれる個性のある小さな本屋さんが注目を集めました。
- 恵文社一乗時店
- ホホホ座(旧ガケ書房)
- B&B
- 誠光社
- ブックスキューブリック
- 天狼院書店 など
本屋さんをやりたい方の中には、こうした独立系書店がきっかけになった方も多いのではないでしょうか?

私が本屋をやりたいと思ったきっかけはヴィレッジヴァンガードでしたが、恵文社一乗寺店や読書のすすめといった特徴的な書店との出会いでその思いはさらに強くなりました。
「本を通して誰かの人生に少しでも良いきっかけを与えたい」。そんな思いを持った方はぜひこの記事を読んで、夢への一歩を踏み出してみてください。
【書店開業を目指す人必読の一冊】
【全国20選】本のセレクトショップ・魅力的な独立系書店を紹介 東京・京都以外にも増加中

【一番気になる!未経験でも本を仕入れることは可能? 新刊・古本の併売も可能】

小さな本屋を開業するためのステップを見てきましたが、一番気になるところは本の仕入れ方法でしょう。
以前は日販やトーハンといった取次店との契約をしないと書店を開くことはほとんど不可能でした。
そして、そうした取次店との契約には数千万が必要と言われており、かなりハードルが高かったのです。
しかし、時代は変革の時にきています。簡単に言うと、
- 安価で取引を始められる取次の登場
- 直接取引を行う出版社の増加
- 新刊だけにとらわれないハイブリッド書店の誕生
この3つが書店業界の新たな変化として現れています。
では、具体的にはどうやって本を仕入れていけばいいのでしょうか?
本の仕入れ方法を、「新刊」「中古本」「ZINE」に分けて解説します。
・新刊の仕入れ方法
新刊は、出版社または取次店から仕入れをして販売します。
取次店は、小さな書店でも安価に始められるところに問い合わせをしてみましょう。おすすめの取次店は、以下の2つです
どんなに小さなお店でも1冊からでも本を仕入れして販売できる仕組みを作った会社です。新刊を扱う書店を作りたいのならば、この2つにコンタクトを取ってみましょう。
また、出版社と直接取引できるところもあります。有名なところでは、
などが直接取引に対応しています。
もしも取次店で取引できない出版社があれば、出版社と直接取引をすることになります。
取次店の扱いがない出版社の本を仕入れたければ、ホームページから直接コンタクトを取ってみましょう。取引可能かどうか、条件があるかどうかを教えてもらえます。
出版社と取次店ともに仕入れ方法は2種類あります。
売れない場合に返品ができる「委託販売制」と、返品はできないけれど仕入れ価格が若干抑えられる「買い切り制」です。出版社や本によって異なります。
買い切り制は売れた時の利益がより大きくなりますが、リスクも大きくなります。始めは委託販売制での取引がおすすめです。
また、出版社の委託販売制の中にも、
- 売れたら売れた分の金額を支払う
- 最初に仕入れ金額を支払って、売れ残った分を返品する時にその分を返金
この2種類があります。

最初になるべく費用を抑えたいのであれば、前者の後払い方式の取引方法を取っている出版社との取引に限定させましょう。
・中古本の仕入れ方法
中古本はブックオフやAmazon、町の古書店などで仕入れます。
最近はメルカリなどにも本の出品が多数出ていますので、そういったサービスを使って購入することもできます。
また、都道府県の古書組合に入って古書の市場で仕入れるという方法もあります。
古書の市場とは、加盟する古書店が自分の店の商品を持ち寄って販売するという形式で、一冊単位ではなく売り合わせ販売になっていることも多いです。
また、中古本を扱う場合には「古物商の資格」が必須になります。
資格といっても必要な書類と2万円程度を警察署で払うだけです。発行までに1ヶ月ほどかかるので早めに取得しましょう。
・ZINE、その他フリーペーパーの仕入れ方法
ZINEは一般的な書店には置いていませんので、販売すれば大きな差別化ができます。
個人の作っているZINEやフリーペーパーを取り扱いたい場合には、基本的には製作者に連絡を取って直接取引することになります。
仕入れをするときには、ほとんどの場合が買い切りとなります。冊数によって値引きに応じてもらえる場合もあるので要確認です。
気になるZINEがある場合は、裏表紙やSNSで製作者を調べて連絡を取ってみましょう。
・本の仕入れ方|具体的なステップまとめ
以上が本の仕入れ方ですが、具体的には以下のステップで進めるのがおすすめです。
- ホワイエ、ことりつぎに問い合わせをして契約する
- 取次に扱いがないけれど置きたい本の出版社やZINEの製作者に問い合わせて仕入れる
- 古物商の申請を出して中古本を仕入れる
ホワイエとことりつぎが出来たことで書店開業のハードルは大きく下がりました。本屋をやりたいという夢は明らかに簡単になったのです。
また、個人の本屋としての色を出すために文房具や雑貨を置くことも選択肢の一つです。
雑貨類の仕入れ方法についてはこちらで解説していますので、よかったら参考にしてみてください。

【個人が本屋を始めるのに必要な資格は?】

本屋を開業するためにはいくつかの資格や許可が必要になります。
しかし、何ヶ月も勉強して取得しなければいけないようなものではなく、届出やお金を払うだけで取得できるものですので、身構える必要はありません。
必要な資格は以下の通りです。
【中古本の販売に必要な資格】
・古物商の取得
・開業届の提出
古物商は警察に申請をして2万円ほどで取得可能。取得まで1ヶ月ほどかかり、許可証が届くまで営業できない。開業届は開業後2ヶ月以内に管轄の税務署に提出する必要があります。
新刊のみの扱いの場合は資格は不要です。ただし、新刊と中古本を併売する場合は古物商も必要になります。
古物商は申請してから発行までに1ヶ月ほどかかります。直前で申請をすると開店日に間に合わないなんて事態にもなりかねませんので、計画的に申請しましょう。
【個人で書店を開業するまでの9ステップ|本屋・ブックカフェの始め方】

それでは、具体的に小さな本屋やブックカフェを開業して本屋さんになるまでの9つのステップを解説します。
結論から言うと以下の9ステップになります。
- 自分の店のイメージを描く(コンセプトや品揃え、ロゴマーク)
- いくらあれば暮らしていけるか調べる
- どうやったら食べていけるかを調べる
- 開業に必要なものと金額の洗い出し
- 開業資金の集め方を考える
- 本屋を始める物件(立地)を探す
- 物件契約・取次業社と契約・古物商を取得
- 物件の改装・商品搬入・備品発注
- 開店

夢に向かって1つ1つクリアしていきましょう。
1、自分の店のイメージを描く(コンセプトや品揃え、ロゴマーク)
まず始めに、自分のやりたい本屋がどういったものなのかを整理しましょう。コンセプトや品揃えの特徴、見た目やロゴマークなどを考えてみるのです。
絶対に置きたい本や揃えたい作家さんから決めていってもいいでしょう。
インスタグラムやピンタレストというSNSを使えば世界中の本屋さんの写真を見ることが出来ますので、外観や内観のイメージはそれらを参考にしてみてください。
また、小さな本屋は営業スタイルも様々です。
- 新刊と古本のどちらを扱うのか?
- カフェやバー的な要素は入れるのか?
- イベントはやるのか?
今の時代の主流は、こうした要素を全て詰め込んだハイブリッドなスタイルです。
明らかに本は売れない時代。集客・経営していくためには本だけでなく別の切り口を考えることも重要でしょう。

考えたことや集めた画像をコラージュして1枚のコンセプトイメージを作ってみてください。そうすると自分の理想の本屋がはっきりと見えるようになります。
2、いくらあれば暮らしていけるか調べる
次に、本屋で生きていくためには実際いくらの費用が必要なのかを知りましょう。
闇雲に始めてもうまくいきません。しっかりと資金計画を立てる必要があります。
例えば、夫婦二人が生きていくのに必要なのは、
- 家賃
- 食費
- 水道光熱費
- スマホ代
- 各種保険
などを合わせて20万円は必要だとします。すると、売上的には以下の金額が必要にあります
- 暮らしていくために必要な20万円
- 店舗家賃
- 店舗の水道光熱費
- 仕入れ代金
- 備品代金
※スタッフが必要な場合は人件費も必要
そう考えるとざっくりと売上目標とすべき数値が出てきますよね。それがわかれば、その売上を達成するにはどうすべきかというフェーズに移っていきます。
ただお店を開業するという目標だけではなく、経営していくための目標を逆算して考えるという思考が重要です。
3、どうやったら食べていけるかを調べる
売上目標がわかれば、それをどうやって達成していくかを考えます。ビジネス的な視点で経営方法を考えるのです。
ビジネスと言っても非常に幅が広いのですが、もっとも重要なのは「マーケティング」だと私は考えています。
・どのようにしてお客さんが来たくなる店にするか
こういったことはマーケティングを学ぶことでヒントが得られます。
また、本屋の経営を考える上で基本となるビジネス思考も理解しておいたほうが良いでしょう。
こうしたビジネススキルは本で学んでも良いですが、動画で学ぶことをお勧めします。
私の場合、ビジネスの勉強のためにグロービス学び放題というビジネス動画サイトを活用しています。
体系的にわかりやすくビジネスの考え方が解説されているのでとても勉強になりますよ。

正直、本屋を始めるだけなら資金と行動力だけで出来ます。しかし、経営を続けていくには売上を上げ続けなくてはいけません。
そのためにはマーケティング力やビジネス思考力が不可欠です。

自分の店を成功させるためにどうやったらいいのかという積極的に知りたいという気持ちがあれば、学ぶことは決して退屈なことではありません。ぜひ今のうちから勉強を始めましょう。
4、開業に必要なものと金額の洗い出し
次に本屋を始めるために必要なものを洗い出します。小さな書店であればそこまで多くのものは必要ないでしょう。
- 物件
- 商品
- 本棚
- テーブル
- 袋
- ラッピング用紙
- ショップカード
- レジ(クレジット対応ががおすすめ)
- 運転資金(毎月の必要経費の半年分くらい)
最低これだけあればお店を開くことが出来ます。
あとは看板やBGM、内装を飾るのに必要なものなどを必要に応じて書き出しておきます。
5、開業資金の集め方を考える
必要な開業資金が決まれば、その資金の調達方法を考えます。
自分の貯金で賄えるのであればすぐにでも始められますが、ほとんどの場合は資金調達が必要でしょう。
親や友人に頼みたくない場合は金融機関からの融資を考えてみましょう。
こちらであれば、初心者でも融資を受けやすいです。
しかし、国民生活金融公庫でも借り入れ金額の1/3は自己資金が必要になる場合が多いです。なので今のうちから貯金をしておくことも開業に向けた1つの準備になります。
開業資金の集め方はこちらでも解説しています。

6、本屋を始める物件(立地)を探す
続いて本屋を開くための物件を探します。「なんか良い物件ないかなー」と漠然と探していても見つかりません。
条件を決めて候補を絞っていく作業が重要です。具体的には、以下のような条件を考えます。
- 出店するエリアを決める
- 店舗物件の大きさ(面積)を決める
- 家賃の上限を決める(物件サイトで相場を掴んでおくと良いでしょう)

私の場合は、田舎だったので「駐車場が確保できること」と「2階に住めること」をを条件として加えました。
条件が決まれば、ネット上の不動産紹介サイトだけでなく、近くの不動産屋さんに電話をして聞いていきましょう。
最初は緊張しますが、見つからないのが当然という気持ちでどんどん電話という作業をこなしていけば慣れます。私も30件以上電話をしました。
候補物件が見つかれば実際に見に行きましょう。
7、物件契約・取次業社と契約・古物商を取得
良い物件が見つかれば契約の手続きを進めていきます。いよいよ夢の本屋開業はすぐそこです。
場所が決まれば、本の仕入れ先や備品発注業者とも契約をしていきましょう。
また、古本を扱う場合は古物商という資格が必要になります。
申請して2万円ほどの費用だけで取れる資格ですが、申請から取得まで2ヶ月ほどかかり取得できるまでは販売できません。早めに申請することをお勧めします。
もしもカフェやバーなど飲食物を扱う場合には、食品衛生責任者の資格も必要です。こちらは1日講義を受けて1万円ほど払うだけで取得できます。
ただし、講義は年に数回しか行われない地域もありますので、扱う可能性がある場合は事前に調べておきましょう。
その他には開業届の提出が必要になります。開業日から2ヶ月後までには提出しなければなりませんので、忘れないよう用意しておきましょう。
8、物件の改装・商品搬入・備品発注
物件契約が済めば、物件をお店に仕立てていきます。改装をして本棚などの什器を入れ、商品を並べていきます。
どんどん自分のお店が出来上がっていく最高に楽しい時間です。この経験は人生のハイライトの1つになるでしょう。
この時点で近隣の方などに直接挨拶に行ったり、SNSで告知しておくことも重要です。
9、開店
いよいよ開店の日です。自分の理想とする本屋に店主として立ちます。
ここまでの解説で、実際に自分の進む道がイメージできたでしょうか?

お客さんと本の話をしたり、新しく入荷した本のチェック、お店に入れたい本選びなど、大好きな本に関わる仕事は本当にやりがいのある仕事になりますよ。
【本屋の経営は厳しくて食べていけない? 続けていくための集客&経営術】

自分の本屋を開いて、毎日好きな本に囲まれた生活。そんな夢の生活は必ず叶えることができます。
しかし、それを続けていけるかどうかは開業とは別問題です。お店をオープンすることは出来ても、お客さんに来てもらえなければ売上は上がりません。
お客さんが来てくれたとしても、誰も買ってくれないと収入は0です。それではすぐに経営が成り立たずに潰れてしまいますよね。
本屋を開業したいと思った時、多くの人は「理想のお店」にフォーカスをして選書やデザインにばかり目が行きます。
経営を考える上で役立つツールに「AISAS」というフレームワークがあります。
- Attention(お店を発見する)
- Interest(興味を持つ)
- Search(ネットで検索する)
- Action(来店する)
- Share(SNSなどで情報をシェアする)
この頭文字をとってAISASです。かなり使い古された考え方ではありますが、今でも経営を考える上でヒントになるフレームワークです。
皆さんも一度これを使って、お店の集客方法について施策を考えてみてください。
「知ってもらったあと、興味を引くためにはどんなことをしたら良いだろうか?」
「ネットで検索する人にどんな情報を伝えたら行きたいと思ってもらえるだろうか?」
「来店されたお客さんがまた来たいと思ってもらうにはどうしたら良いだろうか?」
「SNSでシェアしてもらう仕掛けが作れないか?」
「客単価を上げるためにグッズやカフェ併設、ギャラリーなど、集客と客単価アップにつながることができないか?」
こうしたことを考え続けることが経営です。
答えは1つではありませんし、考えたことが当たる場合もあれば全く効果がない場合もあります。
ヒトの趣味趣向は変わっていきますので、一度成功したことでもその後に効果がなくなる場合もあります。

だからこそ勉強を続けていく必要があります。本についての情報収拾も必要ですが、こうした集客方法や経営術についても学び続けていくことで、改良しながら長く続くお店を作ることができるのです。

【未経験&自己資金0でも今すぐ本屋を始める方法|開業と経営の練習に最適】

書店開業までの9ステップと仕入れ方法を解説してきました。自分の本屋を開くという夢への道のりはイメージできたでしょうか?
とは言え、実際に始めるとなると、ハードルも多いですよね。
- 会社を辞める覚悟がない
- 物件を探す時間がない
- 開業するための資金がない
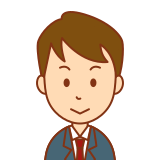
「今は貯金もないし、決断する勇気も持てない。けど出来るなら今すぐやりたいなぁ。」
そんな人におすすめの方法が「イベント限定本屋をやること」です。イベント限定本屋なら大きなリスクを抱えることなく今すぐ自分の本屋を始められます。
数年前からフェスやマルシェなどハンドメイド系のイベントが非常に増えています。そこにみなさんが本屋として出店するのです。
イベント限定であれば、テント一棟ほどのスペースなので、什器も本の冊数もそこまで必要ではありません。
手作りの看板やショップカードを用意するだけでもお店になるのです。
出店料は店舗の家賃に比べて格安なので、費用を抑えた状態で好きな本を仕入れて販売できる。まさに「自分の本屋」の練習が出来るのです。
イベント限定本屋には以下のようなメリットがあります。
- 費用が圧倒的にかからない
- 開業前からファンを作れる
- 自分の本屋が体験できる
- 開業と営業に必要なことが学べる
- 働きながらでも出来る
最近は「BookTruck」のように、イベント出店をメインにしている本屋さんもたくさんあります。
実際に店舗を持つよりもリスクが少なく始められますのでおすすめですし、実際にお店を持つ前の練習としても書店経営を経験できる良い方法です。
イベントに出店する方法には、以下の方法があります。
イベント限定とは言え、自分のやりたい本屋を開くことができたらそれはもう立派な書店店主です。
イベントでお客さんと顔見知りになったら、実際に店舗を持った時の常連さんになってくれる可能性も高くなります。メリットは多いでしょう。
「中古本のみ」で始めるなら始めるハードルはさらに低いです。中古本の販売には古物商の許可が必要とお伝えしましたが、もしも自分の手持ちの本だけを販売する場合は古物商はいりません。
とりあえず今の時点で自分の置きたい本を集めてみて、参加したいイベントを探してみてはいかがでしょうか。

イベント出店の規模であれば冊数も少なくて済みますよね。仕入れの必要がなければ古物商も取らなくて良いので手軽です。
・楽天カードを作って数千円分の仕入れ資金を得よう
イベント出店は本の仕入れ代金の他に、什器代やショップカードを用意すれば簡単に始められます。
しかし、最初に数万円はかかってしまいますので、自己資金0では始められません。ですが、実は自己資金が0でも始める方法があります。
ポイントは以下の2つです。
- 自分の持っている本を商品にする
- 楽天カードを作ってポイントで什器を揃える
自分の持っている本を売る分には、実は古物商の資格が不要。売買目的で仕入れた場合は古物商が必要ですが、私物を売る分には不要なのです。
また、楽天カードを作ると、始めに8000円分(変動あり)のポイントがもらえます。ポイントを使って本棚などを揃えれば、実質無料で備品を購入できます。
楽天ブックスを使えばポイントで本の仕入れも可能ですね。この方法なら自己資金がない方でも始めることができるのです。
楽天カードは開業後の備品購入でも非常に役立ちますので、ぜひこの機会に作っておくことをおすすめします。
以上が小さな本屋を開業するための9ステップと、未経験で自己資金がない人でもできる始め方でした。
本屋を開業するのは難しくありません。ぜひこの記事を参考に一歩目を踏み出してみてください。
【本屋開業 関連記事】

【全国20選】本のセレクトショップ・魅力的な独立系書店を大紹介|東京・京都だけじゃない!
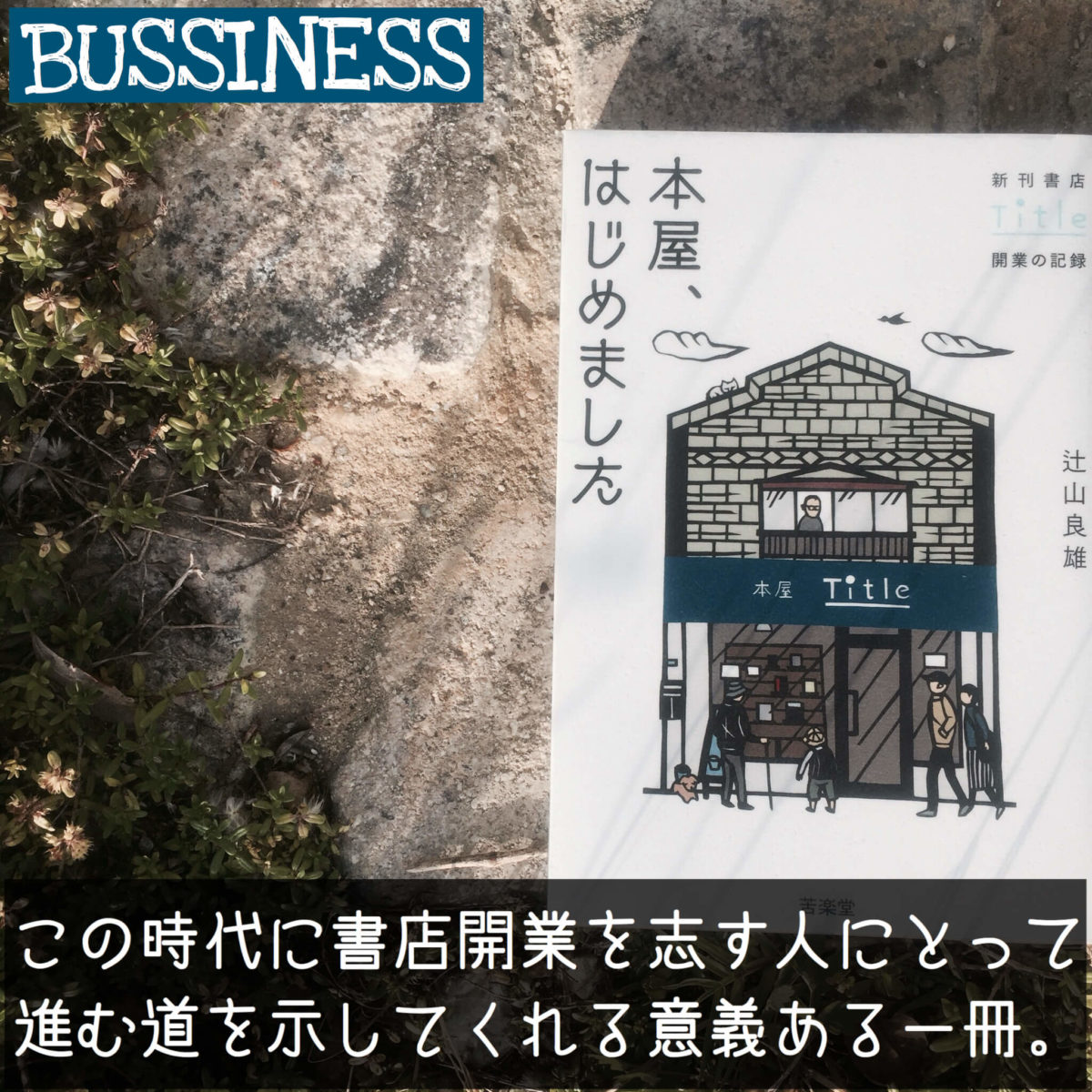
本屋をやりたい人必読!本屋Titleは本屋になりたい人の教科書的存在
【LIFE WORK CAFEのおすすめ記事】
【厳選】キャリア相談が出来るおすすめカウンセリング5選|仕事や転職の悩みが解決する有料サービスを比較
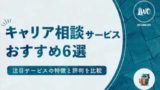
【最新5選】動画編集を副業に出来るスクールはどこ? オンラインでスキルと稼ぎ方を学んで収入アップ

【社会人必見】Webデザインを副業に出来るおすすめスクール5選|Web制作を働きながら学んで最短で稼げる

【7選】稼ぎたいWebライターにおすすめの講座と初心者向けWebライティングスクール|オンラインで副業ノウハウが学べる

【転職向け】Webマーケティングスクールおすすめ5選|未経験からWebマーケターへ就職する最短ルート
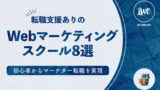
【4選】副業の稼ぎ方が学べるおすすめのオンラインスクール|講座を受講するべきか悩む?